情報社会学部の中村健二教授のゼミ生2チームが、「2023年度 人生100年時代の社会人基礎力育成グランプリ(主催:一般社団法人 社会人基礎力協議会)」に出場。うち1チームが全国決勝大会に出場して準大賞を受賞し、もう1チームは近畿地区大会で奨励賞を受賞しました。
社会人基礎力とは、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力として、2006年に経済産業省が提唱したものです。「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から構成されています。
「人生100年時代の社会人基礎力育成グランプリ」は、この経済産業省の定義に基づいて開催されるイベントで、ゼミ活動などを通して社会人基礎力の育成を図る大学の取り組みや学生たちの成長を競うものです。活動内容だけでなく、学生たちの成長の度合いも評価され、地区予選大会で最優秀賞に選ばれたチームが全国決勝大会へ出場できます。応募チーム数の調整のため、別地区の予選大会に出る場合もあり、今回、大阪経済大学の1チームは東北・関東地区予選からの出場となりました。
中村ゼミでは、情報学や社会学、経営・経済学の学びをもとにビジネスプランを創発し、全国のビジネスプランコンテストや学内コンテスト(ZEMI-1グランプリ)に積極的に応募。過去10年間で56回の受賞を果たし、昨年度の「人生100年時代の社会人基礎力育成グランプリ」でも2チームが全国決勝大会へ出場し、1チームが準大賞を受賞しています。
発表内容
全国決勝大会 準大賞受賞:大阪経済大学1
西村 樹さん、豊田 舜さん、森本 大智さん、庄山 冬聖さん、吉田 壮佑さん
【住まいの日照不足を改善する「日光を用いたICTサービス『ぎゃざらいと』」】
住宅密集地などで日当たりに不満を持っている人が多いことに着目。「自由に日光を届けられれば苦しまずに暮らせる 」と日光に関する新しいサービス開発に取り組みました。最初は鏡などで実験をしたものの思うような結果が得られず、本学の物理学教員のアドバイスを受け、最終的にたどり着いたのは光ファイバーと凸レンズを利用する方法でした。凸レンズと太陽追跡システムで集めた日光を、光ファイバーを通して室内に誘導。さらに、AIとQRコードを用いて目的の場所に的確に光を当てるという仕組みです。これにより、明るさの確保はもちろん、さまざまな日光の効果を得ることができます。
活動にあたっては、メンバーの得意分野に応じて適切な役割分担を行うなど、チームで働くための工夫を行いました。プレゼンテーションでは試行錯誤の過程や実験の様子を丁寧に伝え、「ぎゃざらいと」を使いたいかどうかを調査した結果も紹介。それらの結果、地区予選で最優秀賞を獲得し、2024年3月15日に行われた全国決勝大会で準大賞を受賞しました。
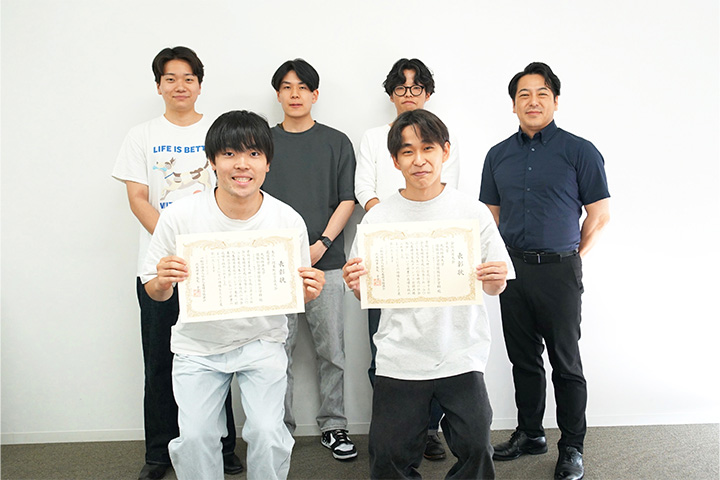
近畿地区大会 奨励賞受賞:大阪経済大学2
大井 樹さん、楠本 善次さん、足立 菜摘さん、田渕 智也さん、穴迫 勇和さん、萩原 一慶さん
【AIとドローンで被害低減を目指す「ICTを用いた獣害対策支援サービス」】
猪や鹿、猿といった野生生物による農作物への被害を防ぐために、AIとドローンを用いた「スマート獣害対策サービス Airosmiss(エアロスミス)」を企画。近畿地区大会で奨励賞を受賞しました。
ドローンを用いた獣害対策は珍しくありませんが、このプランはAIを活用するのが特徴です。田畑などにカメラを設置して常時監視し、AIの画像認識機能で動物の種類を判別。そして、射影変換という手法を用いてカメラ画像から正しい位置座標を算出し、ドローンを向かわせて害獣を撃退するという仕組みになっています。通常、カメラで撮影した画像はどうしても遠近感やズレが生じ、正確な距離や位置を把握できません。そこで射影変換を用いてカメラ画像を俯瞰図に変換することで正しい位置座標を算出でき、実現性の高いシステムにすることができました。害獣を撃退する方法として当初はエアガンを想定していましたが、別のコンテストで航空法に関する指摘を受けて再考。熊スプレーに変更するなど、常にブラッシュアップを続けてプランを仕上げました。
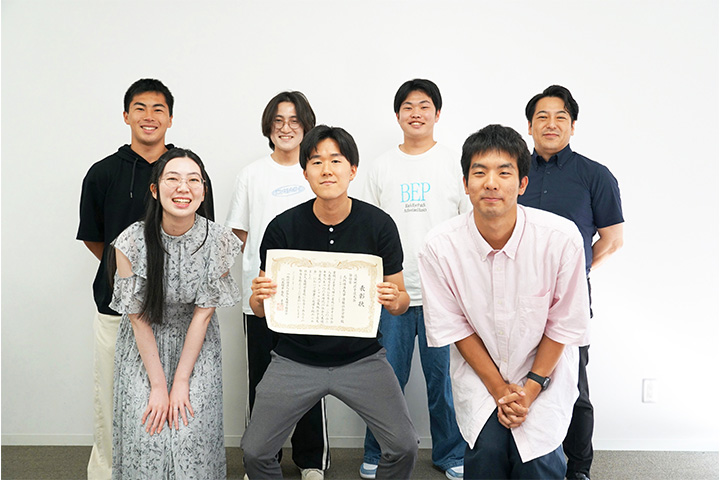
森本 大智さん(4年生) 大阪経済大学1
適材適所を心がけてポジションを分けるようにしてから活動が円滑に進みました。チームで協力して一つのことを成し遂げられたことに成長を感じます。大学近くのショッピングセンターの協力を得てアンケート調査を行ったのも、なかなかできない経験でした。
庄山 冬聖さん(4年生) 大阪経済大学1
失敗を繰り返しながら3カ月くらいかけて実験をしましたが、そのプロセスも評価されたと思います。卒業後はシステムエンジニアとして勤めることが決まっているので、ゼミ活動を通して身についたチームで働く力や、コミュニケーション能力を活かして活躍したいです。
大井 樹さん(4年生) 大阪経済大学2
自分が発案したこともあり、チームの中心となって活動していました。うまく進まないときにはその原因を見つけて対応したり、伝わりやすいプレゼンテーションになるよう工夫したりするなど、いろいろな面で成長できたと思います。発案の段階からカタチにしていくという貴重な経験ができました。
穴迫 勇和さん(4年生) 大阪経済大学2
プログラミングの授業を受けていたものの、一から自分で調べて新しいプログラムを書くのは初めてでした。インターネットで調べたり、他大学の先生にもアポを取って相談したりして、実現性の証明できるシステムになりました。今回の経験は社会に出てからも糧になると思います。


