
100周年ビジョン「DAIKEI 2032」に定める4つのビジョンについて、教職員が深く理解していくことを目的に、各ビジョンと関連する部署を横断して語り合う座談会を開催しています。今回は特別企画として、100周年を迎える12年後に大学生の親となる、学長も含め小学生の子どもを持つ職員が集まり、子どもたちが大学生となる時大学はどんな場であってほしいか、また、子育てをしながら働いている立場からよりよい職場環境についても話し合いました。その内容を前・後編に分けてお伝えします。現代の小学生事情の検証から、親目線でこれからの大学教育のあり方を考えた前編に続き、後編では子育て中の立場から見た働きやすい職場やこれからの働き方について議論しました。
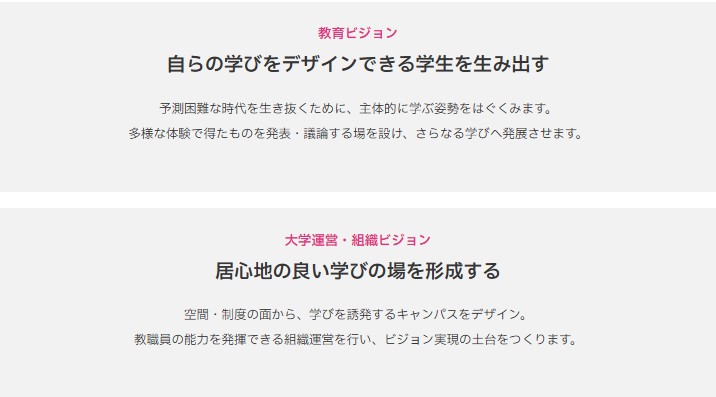
今回の参加者
プライベートな内容が多く含まれるため、学長以外の参加者はイニシャルとさせていただきます。
学長
山本 俊一郎さん
子どもは中学生1人、小学生1人
職員
T・Nさん
男性。子どもは中学生1人、小学生1人
職員
M・Yさん
男性。子どもは小学生3人
職員
T・Yさん
女性。子どもは小学生2人
職員
M・Mさん
女性。子どもは小学生1人、未就学児2人
職員
I・Mさん
女性。子どもは小学生1人、未就学児1人
——子育てをするうえで、大経大はどのような職場でしょうか。子育て中の働き方や工夫していることについての経験も伺いながら、魅力的なところや改善の余地があるところについて考えていきたいと思います。
M・Mさん 私個人の経験でいうと、比較的休みを取りやすい職場です。今の部署には子育てをしている人も多く、急に熱を出して保育園から呼び出しがあっても担当を変わってもらったり、「あとはやっておくから大丈夫よ」と声掛けしてくださったり、とてもありがたいと思っています。その意味で、とても働きやすい職場です。
T・Yさん 私も、前の部署も今の部署でも休む時には気兼ねなく休ませてもらっていて、職場のみなさんには感謝しかありません。
M・Yさん 学校に参観に行くと、来ているお父さんの顔触れはいつも同じです。休みやすい職場、たとえば、市役所勤務の人とかは来ています。私もその一人ということです。
I・Mさん 私も、休みやすいと感じています。担当者しか把握していない仕事があると、イベントなどの時に何かあっても休みづらいというようなことがあるかもしれません。チームで行う仕事や事情を知っている人が他にもいる仕事だと、お任せして休みやすいとかいうのがあるのではないでしょうか。
学長 教員は職員とは勤務体系が違っていて細かく管理されていないので、きちんと休んでいるのかわからないですね。大学に来ていなかったとしても、研究など他の用事があるのかもしれませんしね。
T・Nさん 先生たちは、出産で休むために自分の代わりをしてくれる非常勤の先生を集めるのが大変だとか、代役をお願いすると迷惑をかけるので休みが取りにくいということがあるようです。最近は、介護のために休みたいという要望も出てきました。
学長 ゼミなどでは、副担任制とかがあってもいいのかもしれませんね。
I・Mさん 子育て中の働き方としては、復帰後の時短勤務がありがたかったです。特に、時短期間中でも部署異動の機会をいただき他の部署の仕事について勉強できたのがよかったし、異動先の部署でもいろいろ支えてもらえて助かりました。ただ、時短勤務が利用できるのは、3歳までの子どもを持つ職員に限られます。子育てだけでなく、治療のための通院、介護、孫の世話、勉強のためなど、さまざまなタイミングでフレキシブルに取得できるような制度があればいい、というような要望を持っている人もいるようです。

T・Yさん 私にとっての時短勤務期間は、自分の仕事のやり方、考え方を大転換したという意味で修業期間だったのかなと思います。通常より2時間少ない時間で同じだけの成果を出せるよう、ずいぶん試行錯誤しました。子どもの急な病気などでいつ・どれくらい休むことになるのかわからないため、作成した資料はすべて共有フォルダに保存するようにしました。また、問い合わせを受けた時にファイルの格納場所を答えられるようフォルダを整理し直したり、自分以外の人が見た時にすぐにわかるか?という視点で業務を見える化するなど、仕事のやり方がものすごく変わりました。あとは、職場の同僚への感謝や信頼の気持ちが強くなりました。うちの子たちは、家庭と保育所と職場のみなさんに育ててもらったと思ってます。
M・Yさん 子育てと在宅勤務の両立が課題と言えるのかもしれません。今年から子ども3人全員が小学校に入りました。コロナ禍で子どもらが学校に行けず家にいると、こんなに落ち着かないものかと思いましたね。在宅勤務の時などは、なかなか仕事ができる環境にならないことがありました。
T・Nさん 大経大でも在宅勤務がだいぶん定着してきて、M・Yさんが言ったような子どもが動き回っている中で仕事がしにくいという意見を聞くようになりました。
M・Yさん 在宅勤務を進めている企業の中には、在宅で効率よく作業を進めてもらうためにお手伝いさんを派遣するサービスを導入しているところもあるようです。
T・Nさん 大経大でも、ベビーシッターを派遣してほしいというような要望はありました。また、家では仕事ができないため、インターネットカフェや個室を借りたいといったニーズもあります。学内保育所を設けている大学もありますが、コロナが流行するずっと以前に行った職員アンケートでは、大学まで子どもを連れてくるのが大変だとか、地域から離れてしまうと小学校に上がる時に親子とも馴染みにくいというような意見がありました。また、地域の子どもも通える保育所にするとか、使いたい時にスポット的に使えるようにしたほうがいい、といった意見も出ました。
T・Yさん コロナで休校になるというのは特殊な状況ではありますが、子どもがいる状態で仕事をするというのは難しいですよね。ただ、在宅勤務になって助かったのは授業参観の時。これまでは45分の授業参観のために半日または1日休をとっていましたが、休みを取らなくても、勤務時間をずらすことで対応できるようになりました。
学長 私は、企業などと違って大学の長期休みに合わせ夏と冬に長めの休暇が取れるのが、ありがたいと思います。
T・Yさん 冬休みは、ほぼ子どもと同じ期間休みになりますね。
T・Nさん その時期にみんなが一斉に休むことについて、実は不満もあり、もっとフレキシブルに取れれば、という要望もあります。
学長 子どもといる時間がわりと取れているからかもしれませんが、参観日に仕事を休んで行こう、という気にならないんですよね。もちろん、行ける時は行きます。この間も部活の保護者会に参加したら、120人ぐらいの出席者のうち男性は2人だけ。女性ばかりの中に入るのを少し躊躇してしまいました。
T・Yさん 参観日とかだと夫婦で来ている人をよく見ます。でも、懇談会とかはお母さんばかりかなあ。
M・Yさん 私は、結構参加しています。ただ、女性のほうがコミュニティをつくる力が強いというのもあると思うのですが、私が行っても中に入れない感じがすることがありますね。男女の役割とか、私たちの親の世代から見れば変わったのでしょうが、依然として変わらないところもあるというか。

T・Yさん 親の意識の問題なのか、休めない会社がまだまだ多いのか。
T・Nさん 運動会や参観など、お父さんがたくさん来ているなという印象がありますね。お父さんが来てくれるのを見ている子どもたちは、自分が親になった時にも当たり前に参加するのかもしれません。
学長 子育てを支援するにしても、女性ばかりを対象にすることは徐々になくなっていくでしょうね。ところで、子どもの学校行事に参加するお父さんが増えているにしても、肝心の家事は、どこまでやるようになっているのでしょうか。
T・Nさん 日曜日、家にいる時の昼ご飯の後の皿洗いとか、干してある洗濯物を取り入れるとかですかね。語れるほどはやっていません。
M・Yさん 私は料理ができないので、それ以外のことでできることはいろいろ手伝うようにはしています。洗濯して干す、食洗器に食器を突っ込む、土曜日に掃除機をかけるなど、目に見えるものはいくつかやっていますが、子どもの持ちものチェックをしたりなど目に見えない家事は、妻に頼っていますね。
学長 僕も土日の空いている時はやりますが、平日は、まだまだやれていませんね。子どもってよく「あれがない、これがない」と騒ぎますが、妻に聞くと一発でどこにあるのかわかる。そういう時に、いかに関与していないのかがわかって反省します。
——コロナ禍の対応を経験して、今後も残していくべき取り組み、また強化していくべき取り組みはあったでしょうか。また、働きやすい職場にするためにどのようなことが必要なのか、伺っていきたいと思います。
M・Yさん コロナ禍でオンライン化がぐっと進み、場所や時間に捉われない働き方ができるようになってきました。適切に管理できるのなら、その人にとって働きやすい働き方に変わっていけばいいと思います。ただ、成果の評価の仕方は難しいと思いますね。信用して任せるのか、何か進捗の管理ができるような状況に変えるのか。
M・Mさん 味の素が「どこでもオフィス」というテレワークの制度を導入しています。一日24時間の中でトータル7時間の労働時間を確保できればよくて、時間の取り方は自由なんです。朝6時から7時の間にメールを確認し、家事や子どもの世話をして子どもが登校したらまた仕事をする、といったことも可能です。時間をどうカウントするのかという問題はあるでしょうが、小さい子どもの子育てや介護をしながら働くには、とても魅力的な制度だと感じました。
T・Nさん 裁量労働制に近い感じですね。
T・Yさん テレワークだから、比較的導入しやすそうですね。
M・Mさん 上記の制度なら、長い時間働いているから評価されるのではなく、成果で評価されるような仕組みに変わっていきやすいのではないでしょうか。他社のよい事例から何か取り入れられることがあれば、取り入れていければいいですね。
I・Mさん 出社する日を決めておき、それ以外の日は在宅勤務にしたり休みをとったり自由にできる仕組みを導入し、罪悪感なしに休めるようにしている企業もありました。こういうのは働きやすそうです。子育ての大変さは人によって状況は大きく変わりますし、求めているものもそれぞれ違います。在宅勤務を導入しながら、柔軟にしていくのがいいように思います。

T・Nさん みなさんがちゃんと働くことを前提にした、そういう制度をつくれたらいいなとは思います。もちろん、学生サービスの質や大学としての機能を下げることなく、ですが。
T・Yさん 働きやすさについては、やはり場所と時間に縛られないことに尽きると思います。それと、休職について、今のような病気療養目的だけでなく、留学や大学院で勉強するなど、ステップアップの目的でも使えればいいですね。何年か子育てに集中するために休んで、地域でのネットワークをつくりいろんなものを吸収して戻って来るとか。より建設的な休みという意識がみんなに共有されるといいと思います。
T・Nさん 誰かに仕事のしわ寄せがいくことがないよう、配慮することも大切です。
T・Yさん 超過勤務をしないと処理しきれない業務量がある部署だと、子育てや介護などで自由に時間をやりくりできない人にとっては、働くハードルが一気に上がります。特定の部署に異動できる人とできない人がいるというのは、同質化した人員で部署が構成されてしまって多様性が担保されないし、組織としてバランスが悪い気もします。
学長 そこは今、人を増やして平準化していくことを考えています。また、仕事量だけでなく、仕事の責任が偏るのを回避することも必要です。人に仕事を振り分けて平準化するのは手間がかかりますが、やっていかないといけない。
T・Nさん 今まで当たり前のようにやってきたことを少し変えることで、ピーク時の仕事の山が少し下がったというようなことを、今の部署で経験しました。働き方も含めて、前例や慣習を踏襲して何となくやっていることは見直していかなければならないと思います。
T・Yさん 今回のコロナで、そういうことが見えてきた部分もあるのではないでしょうか。
学長 コロナがあったので、オンライン授業も「はい、やりましょう」とスパっと進みました。今までなら何度も会議をして決めなければならなかったでしょう。テレワークもできることはわかりましたが、対面してやるのとオンラインでは何が違うのかとか、オンラインでできることとできないことを明確にしておく必要があると思います。たとえば、隣で教えてくれるようなOJTが少なくなることの弊害などもあるかもしれません。もう少しコロナが落ち着いたら、職場ごとに整理してみるといいのではないでしょうか。
conclusion
座談会を終えて
職員
T・Nさん
子どもが日々どのように勉強し、遊んでいるのかを知り、自分の頃とは全く違う環境であることに驚きました。彼らには、今の大学の学びや制度にはないようなやり方でないと満足を提供できないのではないかと思います。
職員
M・Yさん
子どもが関心や特性を生かした大学に進学して夢を持って進んでいけるように、親として支援しなければならないと改めて思いました。職場については、長期的なビジョンで人材育成をする必要性を感じました。
職員
T・Yさん
同じ公立の小学校でも環境にさまざまな違いがあり、「日本人の18歳」が想像以上に多様なのかも知れないという気づきを得ることができました。教育ビジョンの柱「多様な価値観が活きる学びの場の提供」実現の重要性を再認識しました。
職員
M・Mさん
自分の子どもが大学生になる時にどうなっているのか、親の方が変化についていけてないのではないかと不安になりました。柔軟に対応できる能力は子どもにも親にも大切。頑張って前向きに考えたいと思います。
職員
I・Mさん
子育て中の働き方や働きやすい環境について、部署を越えて話ができてすごくよかったです。大学の中でのコミュニケーションはとても大切だと感じます。こんな機会があれば、また参加させてもらいたいです。
学長
山本 俊一郎さん
子どもに習い事をさせるのは、何が向いているのかを見つけ、知ってほしいことを学ばせるため。大学生も同じで、社会に出るまでにさまざまな体験をさせ、やりたいことを発見させてあげることが大切なのだと思います。


