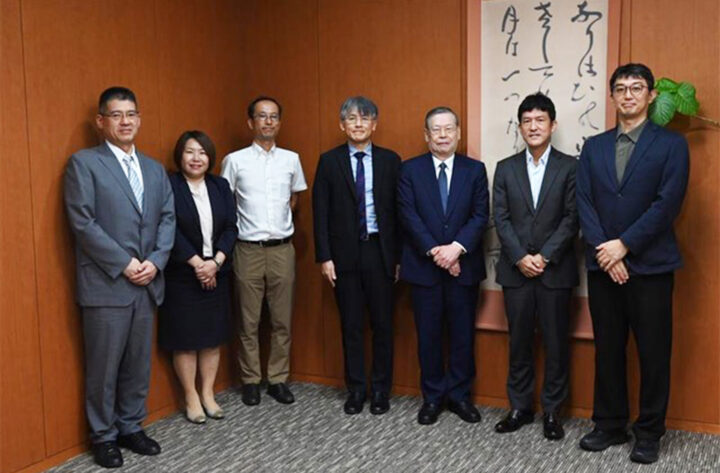大阪経済大学 経営・ビジネス法情報センターは2024年8月22日、東京大学名誉教授の高橋宏志氏を講師に迎え、特別研究会「高橋宏志先生講演会―ビジネスパースンと法的思考―」を開催しました。高橋氏は50年以上にわたり民事訴訟法の研究教育に従事し、法制審議会会長などを歴任。今回の研究会では法律家としての立場から、経済学と法律学との関係、ビジネスパースンと法的思考について講演いただきました。
経営・ビジネス法情報センターは経営学の研究教育に貢献することをめざして2004年に開設され、研究会開催や法律系データベースの提供など、学内外に向けて情報提供活動を行っています。今回の特別研究会も、学生のほか広く一般の方に向けて行われました。

冒頭、高橋氏は次のようにテーマを提示しました。「経済学は効率性を基準にものを考え、法律学は正義を基準にものを考える。基準が異なることから短期的には衝突することもありますが、経済学と法律学は決して対立するものではなく、両立するものだということを最終的には語らせていただきたい」
経済学と法律学が衝突する例として、高橋氏が最初に挙げたのはドストエフスキーの小説『罪と罰』です。貧しく優秀な学生が「お金は自分のところにある方が有効に使われる」と近所の金貸しのお金を奪いますが、経済学的には正当でも、法律学から見れば強盗であり許されません。
もう一つの例として「占有屋」を挙げました。占有屋とは不動産の競売物件に入り込んで占有し、立ち退きを求められると高額な立ち退き料を求めるというもの。占有屋に立ち退きを求めて法的な手続きに費用と時間をかけるより、立ち退き料を払って立ち退かせる方が早く安く済む場合、経済的には後者が合理的です。現在ではこうしたことが起こらないよう法律が整備されていますが、かつては法の網の目を掻い潜って存在したといいます。これも経済的観点と法律的観点がぶつかる事例です。
高橋氏によると、ある大手企業では「100万円以下の債権には手をつけない」と聞くこともあるそうです。占有屋の例と同じく、債権回収のために訴訟を起こす方が費用と時間がかかるというわけです。
ビジネスと法律は、現実の社会でどのように関わり合うのでしょうか。ビジネスの世界にはビジネスの論理、法律の世界には法律の論理があり、それぞれがある程度完結した世界をもちます。しかし、両者は現実世界では重なり、双方向の交流があるため「法律がビジネスを規定し、ビジネスが法律を変えるという側面もある」と高橋氏は言います。
その一例が、株主代表訴訟です。会社の経営者が不正を行って会社に損害を与えた場合、株主が会社経営者に対して損害賠償を請求できる制度ですが、訴える際の手数料が高いことや証拠が手に入りづらいことなどからなかなか使われる機会がありませんでした。1985年頃から手数料が大幅に引き下げられ、会社は情報を出すべきという動きも強まり、一気に盛んになったといいます。法がビジネスに強い影響を与えた例です。
逆に、ビジネスの要請で法が変わったのが「金庫株(自己株)」です。会社が自社の株を持つことを金庫株と呼び、不正防止の観点からかつては禁止されていましたが、会社にとって一定のメリットがあるため、ビジネス界からの要請を受けて今では適法になっています。
「担保権」もビジネスが法を動かした例の一つです。担保権は債務者が破産した場合に債権を回収できる権利ですが、中世の頃は債務者と担保権者の痛み分けのような制度だったといいます。現在のように担保権が絶対的に優遇される制度に変わった背景には、金融関係の債権者の強い要望があったそうです。
経済学と法律学は互いに影響し合い、ときにぶつかることがありますが、企業に就職したビジネスパースンは、法律とどのような関わりをもつことになるのでしょう。業種ごとに定められた業法や会社法など、「会社のどの部署に配属されても法律は必ず関係する」と高橋氏は言います。
配属された部署で出会う法律は現場で身につけていくことができますが、大きな事案になると弁護士が登場します。このとき、弁護士と会社との対話を理解するためには、法的なものの考え方が身についているかどうかが大きく影響するといいます。
「法は究極的には常識、ということをよく言われますが、一般常識だけでは処理しきれないこともあります」。高橋氏はそう言って、次のような事例を紹介しました。骨董品盗難の被害に遭った人が、公正な市場でその骨董品を購入した人から取り戻すというケースです。一般常識で考えるとどちらも被害者ということになりますが、この場合はどう考えればよいのでしょうか。
法的なものの考え方の一例として高橋氏が示したのは「正当な手段で骨董品を購入した人に対し、もとの所有者がその購入費用を支払うことで、骨董品を取り戻すことができる」というものです。「もとの所有者は、お金は払わなければなりませんが、骨董品を取り戻すことはできる。もう一方の人は、骨董品は手放しますが、骨董品を購入した費用は手元に戻る。こうした形で全体のバランスをとるのが、法的なものの考え方の一例です」
この内容を一般化すると、法的なものの考え方とは「正義を基準にバランスを考えてものごとを処理し、出てきた結論を、筋道を立てて説明することができること」。法律や弁護士制度、裁判所制度は国によって異なりますが、だからこそ基本的な法的思考は大切で、そうした考え方が自然に身についていくのが民法や刑法の学習だといいます。
昨今、日本を代表するような大企業でのデータ不正などのニュースを目にすることがあります。ビジネスパースンがなんらかの不正に気づいた場合、どのように対処すればいいのでしょうか。高橋氏は「制度としての法律が整っていても、使いやすく万全なものかというと必ずしもそうとも言えない」として、二つの例を挙げました。
一つ目が、発展途上国での賄賂の例です。発展途上国でビジネスをしようとすると公務員に賄賂を送らなければ許可されないようなケースがあり、「賄賂を渡してよいと考える人はいませんが、ビジネスは成功させなければならず、そこでひどい葛藤に陥ることになります」
もう一つは、公益通報(内部通報)の例です。公益通報制度は表面的には整っていますが、実際にどれだけ機能するかというと、難しい問題があります。日本では、公益通報しようとするとき「周りの人間にどう思われるか」「協調性がないなどと思われるのではないか」と葛藤が生まれ、二の足を踏んでしまいがち。上司や同僚を売るというようなイメージもあります。「内部通報に対するこうしたネガティブな捉え方は、日本では一般的に見られる組織風土という面もあります」と指摘します。
内部通報者に不利益を与えてはならないことは法律で定められていますが、実際には企業は密かに犯人探しをして通報者を特定することが少なくなく、人事異動で自主的に辞めさせるなどの嫌がらせがあるのが現実だといいます。公益通報しない方が経済的には賢いということになりますが、明らかに違法なことが行われている場合、当事者はジレンマに陥らざるを得ません。
高橋氏はこれについて「万人にお勧めできる正解のようなものはないのでしょう」としつつ、長い目で見れば公益通報は企業自身のためになるといいます。ボヤを小さいうちに消せばボヤですみますが、放っておけば大火事になりかねません。不正違法が原因で最終的に倒産してしまった企業は現にたくさんあり、そのようなことを防ぐために公益通報は役立ちます。長い目で見れば矛盾でも対立でもなく、「経済学と法律学は短期的にはぶつかることがあるかもしれないが、長期的に考えれば両立する」というのが高橋氏の結論です。
空気をうまく読むのがビジネスパースンであり、空気を読まない、あるいは読んではいけないのが法律家だ、と言われることがあるそうです。「私なりにこの言葉を読むと『法的素養を備えたよきビジネスパースンは、空気を読む力はなければならない。しかし、読んだ空気に流されることもない』。これが法的素養を備えたビジネスパースンのあり方だと考えます」
中国には「天網恢々(てんもうかいかい)疎にして漏らさず」ということわざがあり、天の正義の網は粗くても、悪いものは漏らすことなく罰することを意味します。このことわざを例に、高橋氏は「こういうことが経済と法律の間でも成り立つのではないでしょうか」と説きます。
最後に高橋氏が触れたのが「経済学の父」とよばれるアダム・スミスです。アダム・スミスは『国富論』と並んで著名な『道徳感情論』という著作も残し、グラスゴー大学で道徳哲学の教授として倫理学や法律学も教えていたといいます。アダム・スミスにとって経済学と法律は対立するものではなく両立するものと理解されていたことを紹介し、「大きなものの考え方としては経済学と法律学は両立する」と講演を締めくくりました。なお、講演後に法学検定試験委員会事務局長の岩佐智樹氏より、法学検定試験の詳細な説明と受験に向けた案内がありました。
経済学と法律学の衝突やジレンマは、社会で実際に出会う可能性のあることです。今回の講演では法律家としての見識に基づき、豊富な事例を通して中長期的なものの見方やバランスのとれた法的思考などが示され、一般の方にとってはもちろん、これから社会に出る学生にとっても大変有意義な内容でした。