2024年11月11日、日本銀行理事、大阪支店長の神山一成氏を講師にお迎えし、公開特別講座を実施しました。経済学部 福本智之教授が担当する「金融政策特論」の授業の一環として本学学生が受講したほか、金融・経済に興味をお持ちの一般の方々にも聴講いただきました。日本銀行で多様な業務に従事してこられた神山氏は、「フォーカスBOJ(日本銀行)」と題し、日本銀行の業務や役割、金融政策を詳しく解説され、日本経済と関西経済のこれまでの動きや今後の見通しについてもお話いただきました。

神山氏は講演の冒頭、入行以来30数年間に自身が携わってきた業務の数々を紹介しました。入行まもなく配属された発券局では、貨幣の流通業務の機械化に取り組みました。その後、企業の協力を得て景気の実状を把握する産業調査に携わったほか、国内経済を分析して情報発信する調査統計局、金融政策について検討する企画局、金融システムの安定に向けて金融機関の健全な経営の維持を目指す金融機構局の業務に従事。決済機構局では中央銀行デジタル通貨の実証実験に取り組み、国際局ではウクライナ問題や為替円安への対応を考えたといいます。「こうした私の経歴から、日本銀行が多様な業務を行っていることが分かっていただけるかと思います」と話しました。
「銀行の銀行」「政府の銀行」「発券銀行」という中央銀行としての役割など日本銀行の基本情報を説明した上で、1998年に施行された「改正日本銀行法」について解説。この改正により、日本銀行の政府からの独立性が明確化されたと言われています。日本銀行が景気の現状を判断し、それに基づいて自ら政策を決定し、業務を行うという日本銀行の役割が法律で明確にされたということです。また、政策の決定内容や決定過程の透明性を高めることも改正日本銀行法の重要な理念と定められています。「日本銀行は認可法人です。日本銀行員は公務員ではなく、ましてや選挙で選ばれたわけでもありません。政府から離れて自主的な判断を行うにあたっては、我々の考えを国民に明らかにして透明性を確保することが重要です」と、神山氏は説明します。
改正日本銀行法では、日本銀行の目的も明確に示されました。「お金の価値が安定している状態にする『物価の安定』、お金のやりとりを行う仕組みがいつでもうまく働くようにする『金融システムの安定』を実現するのが、日本銀行の役割。分かりやすく言うと、人々が安心してお金を使えるようにすることにより、わが国の経済の安定的発展に貢献するということです」
では、「物価の安定」をどのように図るのでしょうか。現代社会で流通している貨幣そのものには価値はありません。中央銀行が市場に流通するお金の総量や金利などを調整する金融政策を実施することにより、インフレでもデフレでもない「物価が安定」した経済を実現しています。
神山氏によると、日本銀行が考える「物価の安定」とは、「家計や企業等のさまざまな経済主体が物価水準の変動に煩わされることなく、消費や投資などの経済活動にかかる意思決定を行うことができる状況」だといいます。「例えば、物価の上昇が見通せないから、今すぐ買っておこうといった行動をすることが、物価変動によって煩わされているということ。物価については、こうした状況は好ましくないとの考えです」
日本銀行が目指しているのは、緩やかな物価上昇のもとで前向きに循環する経済の形です。「以前は世界の中央銀行において、緩やかであれば物価下落は許容できるのではないかという考えがありました。しかし、日本が実際に緩やかなデフレを経験する中で、物価が下落すると景気が弱くなりやすいと分かりました。現在は、単に物価だけが上がるのではなく、経済活動が活発化し、賃金や企業の利益の上昇を伴う形を目指しています」
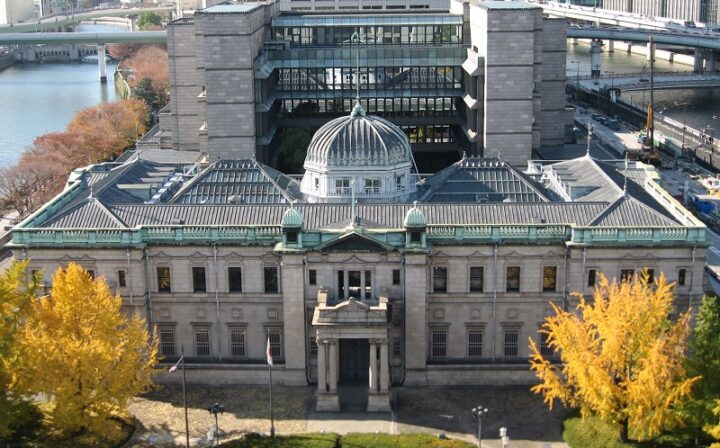
次に神山氏は、バブル崩壊以降の日本経済が直面した課題と金融政策について語ります。いわゆる「失われた20年」と呼ばれる期間の状況を振り返りました。バブル崩壊以降、日本経済は潜在成長率と物価上昇率の両方が低下。どちらも、従業員が企業から受け取る名目賃金を押し下げる方向に働きます。1980年代後半には日本の潜在成長率は4%程度ありましたが、1990年代に入って低下していき、2000年代には1%を切る水準にまで低下しました。日本銀行はデフレ対策として金融緩和を実施した結果、短期金利は1990年代後半にゼロに達しました。
通常の金融政策では、経済の状況に応じて短期の金利を上げたり下げたりします。しかし、短期金利をゼロまで引き下げても十分な効果が得られなかったため、日本銀行は「非伝統的な金融政策」に取り組みます。主な手段は、長期金利の引き下げ、マイナス金利政策、日本銀行による資産購入の3つです。2013年には消費者物価の前年比上昇率2%の「物価安定の目標」を導入。当時、企画局に所属していた神山氏は、この政策に関する議論に携わっています。日本銀行は目標の実現に向け、量・質ともに次元の違う「量的・質的金融緩和」を導入し、デフレ脱却を目指しました。
これらの「非伝統的金融政策」の目的は、「どんどん上がっていく可能性のあった企業倒産、失業者数の増加を防ぎ、社会の安定を図ることにありました」と、神山氏は説明します。「他国の中央銀行が導入しなかったような思いきった政策を導入したことで批判の声もありましたが、我々はこうした政策が日本経済のためにどうしても必要だと考え、取り組んできました。実際、企業倒産、失業者数ともにかなり低い水準が続いており、一定の効果があったのではないかと考えています」
一方、企業の立場から見た過去20年の状況はどんなものだったのか、日本銀行が今年行った大規模なアンケートから明らかにします。「企業倒産を回避するために金融緩和を続けていた影響で、企業間の競争が厳しく、価格競争によってコスト上昇分を価格転嫁することが難しい状況でした。そこで企業は、利益の減少、調達先への値下げ要求、人件費の抑制を行い、コスト上昇に対応せざるを得ませんでした。将来のための投資を行うこともできないという状況が続いていたということです」
しかし、最近では企業の考え方が変化し始めていることがアンケート結果から分かります。「事業活動上好ましい物価と賃金の状態」について聞いた設問には、大多数の企業が「物価と賃金がともに緩やかに上昇する状態」と回答しています。その理由としては、「賃金が増えると家計のマインドや消費にプラス」「価格転嫁が容易になり収益を確保しやくなる」「値上げを抑制するためのコストカットが不要になり、前向きな設備投資や賃上げを行えるようになる」といった答えがあげられていました。

コロナ流行以降の現状、今後の経済と金融政策の展望にも神山氏は言及。コロナ明け、とくにアメリカの中央銀行が利上げする中で円安化が進み、一時期は160円近くに達するという状況がありましたが、日本銀行は利上げに踏み切りませんでした。これについて神山氏は、「日本銀行が目的とするのは、国内物価の安定です。円安化に関して日本銀行の金融政策をあてるべきではないとの考えです」と説明します。
2022年から2023年にかけては円安が進む中で輸入物価が前年比50%近く上昇し、これを受けて日本の消費者物価も上がりました。「この状況下で、米欧の中央銀行と同様に日本銀行も利上げしてもよいのではないかという議論がありましたが、2023年の時点では時期尚早ということで日本銀行は動きませんでした。これは、主に消費者物価を押し上げている要因はエネルギー価格であり、いずれ価格は下落し、消費者物価の前年比も下がることが見込まれたからです。消費者物価の前年比上昇率2%の目標値を持続するために、まだ金融緩和が必要だという判断でした」
また、この段階では、物価上昇率を差し引いた実質賃金がマイナスだったことも金融緩和を継続した背景の一つです。企業では少しずつコストを価格転嫁し始めていたものの、まだコストの上昇分をカバーしきれず、物価上昇率ほどに賃金を上げられない状況でした。こうした状況下で個人消費は弱い状況が続いており、利上げに踏み切らなかったといいます。
ようやく2024年に入ってから名目賃金がプラスに転じはじめ、日本銀行もこれまでの政策から転換を図る決断をします。3月には非伝統的金融政策の一つであるマイナス金利を解除し、7月には政策金利を+0.25まで上げました。
今後の金利水準の引き上げについては、「緩やかな金利上昇を見込んでいる」と神山氏は強調します。「20年以上ずっと低金利状態が続いてきたので、これを変えていくには一歩一歩、想定外のことが起きないかを確認しながら進めていく必要があると考えています」と話しました。

最後に神山氏は大阪支店長として、関西経済の現状認識を示しました。「一部に弱めの動きが見られるものの、緩やかに回復しているというのが関西の景気の現状であると見ています。これは、全国と変わらない状況です。今年4月の段階では、主に中国との競合が強まって輸出の数字が悪く、全国対比で弱めの判断でしたが、現在は持ち直しはじめています」
中国との競合、人手不足という課題があり、「需要が強いからといってやみくもに生産を増やしていける状況にはない」と、神山氏は指摘。「企業は、不採算部門は撤退し、より収益を上げられる部門へと人をシフトさせていっています。その結果、数量としては輸出も生産も強くはありません。一方、収益の面でいうと、製造業の企業収益の水準はしっかりと上がってきています。従来は雇用を抱えている中で不採算の事業でも続けるという選択をしていたのが、今は人手不足なので思いきって撤退することができ、収益が改善しています」
設備投資に関しては、新製品開発、研究開発の投資を中心に積極的に設備投資していると説明します。とくに公共投資は全国と比べて1.5倍ほどの水準にあり、関西経済の先行きにつながる好材料となっています。万博に関連し、大阪駅前の開発、交通インフラ整備、ホテル建設などが活発に行われています。
この勢いが万博後も続くかどうかが重要な論点ではありますが、神山氏は楽観的に捉えていると話します。「関西国際空港からの入国者数はコロナ禍前である2019年の水準を超え、着実に増えているからです。外国人一人当たりの消費額は全国平均より高く、大阪と京都を合わせると東京に匹敵する数字となっています。万博がまだ始まっていない段階での数字ですから、外国人をひきつける魅力が関西にはあるのでしょう。現在、人手不足によってホテルの稼働率が80%にとどまっていますから、万博に向けて人手を確保することが課題です」と、関西経済の今後への期待を語りました。
日本銀行の金融政策について表面的には知っていても、どのような考えのもとで行われているのかまでよく理解していない人は多いのではないでしょうか。今回の神山氏の講演で政策の背景を学んだ聴講者は、今後、経済・金融の動きをより深く理解するために大きな助けとなる知識を得られたことでしょう。


