2025年1月23日(木)、本学の総務課職員であり、京都市の消防団員や防災士としても活動する浪花氏が、大阪市東淀川区の豊里南小学校を訪問し、防災に関する出前授業を実施しました。本学は地域と連携しながら防災意識の向上に取り組んでおり、この授業もその一環として行われたものです。特に本学が所在する東淀川区は、地震や水害などの災害リスクが高い地域であるため、防災に関する知識や備えの重要性を伝えることが求められています。

豊里南小学校の4年生は、南海トラフ巨大地震の被害予測を学び、防災の重要性を実感。その後、「防災とは何か」「どのような備えができるのか」を考える総合学習を進めてきました。その取り組みの一環として、大阪経済大学の出前授業が実施されました。本授業では、小学生たちが事前に調べた防災に関する質問に浪花氏が答える形で進められました。子どもたちからは、防災リュックの中身や避難時の行動、ペットの避難、寒さ対策、トイレの問題など、実際の避難生活を想定した具体的な質問が多数寄せられました。
例えば、「防災リュックには何を入れるべきか?」という質問に対し、浪花氏は「水や食料はもちろん、懐中電灯やラジオ、ビニール袋なども重要です。防災頭巾やヘルメットの代わりに、簡易的に頭を守れるものを準備するといいですよ」と説明しました。また、「寝ているときに地震が起こり、足が挟まれたらどうすればいいか?」という質問に対しては、「大きな声を出せなくなったときのために、笛を枕元に置いておきましょう」と実際に防災グッズを使いながらアドバイスしました。
さらに、避難時に足元を守るため、靴をベッドの近くなどに置いておくことも推奨しました。地震の際には、割れたガラスや瓦礫が床に散乱する可能性があり、素足のまま避難すると怪我をする危険があります。靴をすぐに履けるよう準備しておくことで、安全に避難できることを伝えました。

大阪経済大学では、約8,000人の学生や教職員が災害時に3日間安全に過ごせるよう、十分な食料や水を備蓄しています。さらに、キャンパス内では地震発生時の避難訓練や防災講習会などを実施し、学生や教職員一人ひとりが適切な行動を取れるような環境を整えています。浪花氏は、「大学では防災意識を高める取り組みが進んでいますが、それは小学生や地域住民にとっても重要なことです。防災は“自分の身を守る”ことから始まり、最終的には“周囲の人を助ける”ことに繋がります」と話し、日頃からの備えの大切さを強調しました。
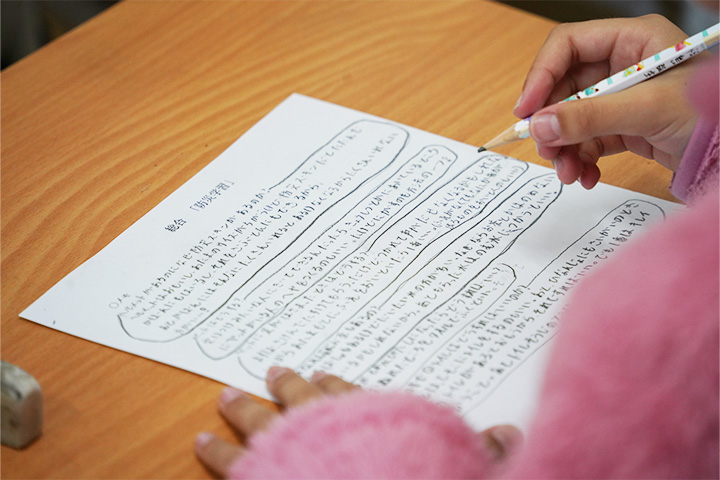
授業の最後には、浪花氏から「まずは自分の身を守ることが最優先。そのために、日頃から健康な体をつくることも大切です」とのメッセージが送られました。また、子どもたちが「家族と集合場所を決める」「避難時の持ち物を考える」といった、家庭でできる防災対策から実践することを促しました。防災教育は、災害が発生した際に命を守るための重要な取り組みです。今後も地域の防災活動に積極的に関わり、防災意識の向上に貢献していきます。


