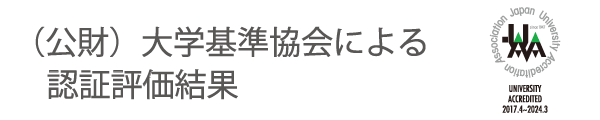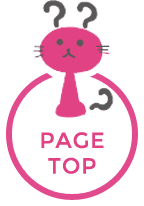2021/10/25②
2021/10/25②
「養成課程修了生さんを訪ねて」第3回西島誠さん後編(独立診断士編)
こんにちは。「養成課程修了生さんを訪ねて」シリーズ担当の、3期生岡本です。
前編に引き続き、1期生の西島誠さんにご登場いただきます。診断士の仕事や専門性についての話になりました。「自分の専門って何だろう」と悩まれる志願者の方もいらっしゃると思います。一つ一つ言葉を選びながら誠実にお話してくださいましたので、参考になれば幸いです。
Q1.現在のお仕事内容について教えてください。
A1.独立前からの知り合い2社からお声がけ頂き、会社の顧問を引き受けています。他には金融機関からの紹介で補助金の仕事をしています。また、在職中に社会保険労務士の資格を取得していましたので、人事系の仕事も依頼があればお受けしています。
Q2.診断士の仕事・専門性について。
A2.
①仕事について
「診断士の仕事って何ですか?」とよく聞かれますが、定義が難しいですよね。例えば補助金の仕事は「診断士らしい、らしくない」など意見が分かれます。でもそこは垣根を作らず、自分のため、相手のためになる仕事が出来ればよいと考えていて、「どうあるべきだ」ということはあまりこだわらずにやっています。しかし、納得できない仕事はやらないようにしています。独立したメリットは、納得いく仕事が出来ることだと思うので、そこは意識するようにしています。周りから「コロナで辞めたら仕事無いで」と心配されましたが、診断士の仕事は増えています。
➁専門性について
「専門は何ですか?」これもよく聞かれますね。養成課程に通っていると「何を強みにするのか。専門や得意分野を持ちなさい」などと言われませんか。実は、私には未だ一般的な専門や得意分野はありません。最初は専門が無いことを気にしていましたが、それよりも「自分が今までやってきたこと」が大切だと気づきました。付け焼刃で知識を付けても実践が伴っていない知識は、底が知れています。世の中に同じ人はいないので、自分がやってきたことがどんなことでも専門分野なんだと気づきました。ですから、必ずしも一般的な専門がなくてもやっていけると思います。診断士は俯瞰的に見て、企業様の課題を見つけて、学んだ知識と今までの生き様をブレンドして、課題解決のお役に立つことができればよいと考えています。
Q3.現在のお仕事において養成課程で学んだことが役立っていますか。
A3.まずは、実際に企業様に行った際のヒアリングの手法を学べたことですね。相手の方との接し方や、事前準備はどこまで行うのか、そして、ヒアリング後にどのように修正すればよいのか、という感覚を身に付けられたことは非常に大きいと感じています。
次に、報告書の書き方ですね。自分の文章はどんな癖があるか、読んでみてどう感じるのかを、客観的に見ることができるようになりました。他の受講生のレベルを勉強させて頂いて、刺激を受けました。みんなからの指摘を受けての気付きは非常に大きく、得難い経験となりました。
◎養成課程の受験を検討されている皆さまへ一言
なぜ診断士になると決めたのか、将来どういう診断士になりたいのか、ということを中心に考えて選ばれるのがよいと思います。
養成課程では、実際に活躍している先生方から学ぶことが出来る上に、接点を持つことが出来ます。診断士として活躍したいとお考えならば、修了生の立場として養成課程を選ぶことをお勧めします。
養成課程は時間や経済的に負担はありますが、それ以上の経験が出来ますし、得るものが大きいと思います。大経大の養成課程は概ね北浜で実施されるので、仕事をしながら通えることが一番よかった。私は仕事をしながらであれば1年が限界だと思っていたため、1年で修了出来ることが決め手になりました。実践的な知識を身に付けられたことも大きな収穫で、求めていたものがここにはありました。
**取材を終えた感想
西島さんからは、「養成課程で学ぶ機会を得られてとても感謝しています。こうやってお話をすることで、少しでもご恩返しになるのならば、喜んでお話させて頂きます」とおっしゃって頂きました。この場をお借りして、お礼申し上げます。