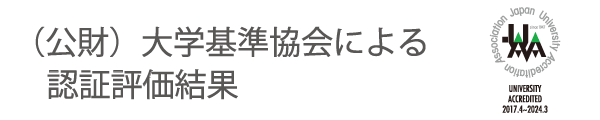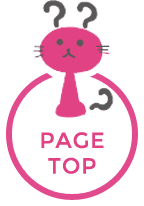活動・セミナー報告
人間科学研究科活動報告
●大学院ゼミ活動
チャレンジ!!オープンガバナンス2024
2025年4月16日更新
人間共生専攻の高井ゼミ報告
〇場 所:東京大学(本郷地区浅野キャンパス)
〇日 時:2025年3月16日(木)10時~18時
〇アイデア名:子育てママ・パパも外国人、高齢者も「Plus防災」でゆるくつながる
「チャレンジ!!オープンガバナンス2024」(COG2024)
データ・デザイン・デジタルで地域課題解決に市民が迫る!
〇資 料:スライドへのリンク
https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2024/
人間共生専攻M1の鄭 芳さんと傅 暁麗さんが学部生と協力し、COG2024コンテストに応募、そして最終選考に進みました。COG2024は東京大学が主催となり、行政が抱える地域課題に対し、学生や市民がアイデアを出し、行政と共に課題解決に取組むコンテストです。110団体がエントリーし12団体が最終選考へ。学生も東淀川区役所地域課の土井聡さんも熱く発表。残念ながら賞には手が届きませんでした、防災活動を通じ留学生と地域の外国籍住民がつながるアイデアをしっかりと提案しました。
●大学院ゼミ活動
畿央大学大学院と合同ゼミ発表
2024年9月10日更新
人間共生専攻の高井ゼミ報告🔹2024年7月25日(木)18時30分~20時30分
畿央大学大学院健康科学研究科の高取克彦教授のゼミ生と大阪経済大学人間科学研究科の高井逸史教授のゼミ生と合同でゼミ発表を実施しました。畿央大学同研究科の松本大輔准教授も出席されました。
高取ゼミの院生は皆さん理学療法士の資格をもち、病院や介護保健施設などに勤務しながら研究を進めています。
高取ゼミから院生3名が研究の進ちょく状況を発表しました。
テーマ1「回復期リハビリテーション病棟入院患者の転倒恐怖感と身体活動量との関係について」
テーマ2「認知症患者の身体機能自己認識の誤差と転倒発生との関連性」
テーマ3「介護老人保健施設における「笑いヨガ」介入が身体機能および心理機能に及ぼす影響」
一方、高井ゼミから院生3名が出席し、M2の張倩さんが研究内容を発表しました。
テーマ「介護予防の視点から在日中国人向けのデイサービスに関する質的研究」
張さんは9月入学のため、8月末までに研究論文を提出し、8月9日には最終発表があります。そんな中、今回研究発表をしていただきありがとうございました。
畿央大学大学院健康科学研究科の高取克彦教授のゼミ生と大阪経済大学人間科学研究科の高井逸史教授のゼミ生と合同でゼミ発表を実施しました。畿央大学同研究科の松本大輔准教授も出席されました。
高取ゼミの院生は皆さん理学療法士の資格をもち、病院や介護保健施設などに勤務しながら研究を進めています。
高取ゼミから院生3名が研究の進ちょく状況を発表しました。
テーマ1「回復期リハビリテーション病棟入院患者の転倒恐怖感と身体活動量との関係について」
テーマ2「認知症患者の身体機能自己認識の誤差と転倒発生との関連性」
テーマ3「介護老人保健施設における「笑いヨガ」介入が身体機能および心理機能に及ぼす影響」
一方、高井ゼミから院生3名が出席し、M2の張倩さんが研究内容を発表しました。
テーマ「介護予防の視点から在日中国人向けのデイサービスに関する質的研究」
張さんは9月入学のため、8月末までに研究論文を提出し、8月9日には最終発表があります。そんな中、今回研究発表をしていただきありがとうございました。
●「産学公連携」事業
[概要]
私たち教員は自治体をはじめ、企業や団体と連携し、課題解決をめざし
関連分野の研究や活動を進めています。こうした「産学公連携」事業に
学生も参画することで、座学では学べないリアルな実践を学ぶことがで
きます。人間科学研究科ではこうしたリアルな実践力が学べることも大
きな特色です。FD研修を通じ、教員同士で「産学公連携」のあり方を共
有しています。
関連分野の研究や活動を進めています。こうした「産学公連携」事業に
学生も参画することで、座学では学べないリアルな実践を学ぶことがで
きます。人間科学研究科ではこうしたリアルな実践力が学べることも大
きな特色です。FD研修を通じ、教員同士で「産学公連携」のあり方を共
有しています。
◆事例報告(2023年度FD)
2024年4月9日更新
【日 程】2024年1月13日(金)
【テーマ】「学生(留学生)が地域の健康づくりを通じて学んだこと」
【登壇者】髙井逸史教授
【概 要】学生(留学生)が主体となり、包括連携協定を締結するUR都
市機構の団地に住む高齢者の体操クラブを創設した。コロナ
禍により、高齢者の孤独・孤立が問題となっていた。そこで、
介護分野を専門とする留学生が交流を通じ学んだことを報告
した。
2024年4月9日更新
【日 程】2024年1月13日(金)
【テーマ】「学生(留学生)が地域の健康づくりを通じて学んだこと」
【登壇者】髙井逸史教授
【概 要】学生(留学生)が主体となり、包括連携協定を締結するUR都
市機構の団地に住む高齢者の体操クラブを創設した。コロナ
禍により、高齢者の孤独・孤立が問題となっていた。そこで、
介護分野を専門とする留学生が交流を通じ学んだことを報告
した。
【資 料】スライドへのリンク
◆事例報告(2022年度FD)
【日 程】2024年2月26日(月)
【テーマ】「産学公連携を通じた学生への学び」
【登壇者1】田島良輝教授
【概 要】大阪府交野市と大阪経済大学との包括連携協定に関する事例
報告を行った。
・協定締結によって実施した教育プログラム「子どもたちの夏休
みを消化時間にさせない!夏休み水泳&宿題教室」の成果報告
・包括連携協定締結を実現したプロセスの提示
・企業や自治体との包括連携協定のアプローチアイデア、メリッ
ト等のまとめ
【日 程】2024年2月26日(月)
【テーマ】「産学公連携を通じた学生への学び」
【登壇者1】田島良輝教授
【概 要】大阪府交野市と大阪経済大学との包括連携協定に関する事例
報告を行った。
・協定締結によって実施した教育プログラム「子どもたちの夏休
みを消化時間にさせない!夏休み水泳&宿題教室」の成果報告
・包括連携協定締結を実現したプロセスの提示
・企業や自治体との包括連携協定のアプローチアイデア、メリッ
ト等のまとめ
【資 料】スライドへのリンク
【登壇者2】大橋純子教授
【概 要】行政機関、企業、地域ボランティアと協働による閉じこもり傾
向の母子や高齢期の外出を促す個人要因へ働きかける地域支援
への取り組み
研究のきっかけは、地域にはボランティアが中心となり住民の
外出や顔見知りの機会を設けるカフェサロンなど様々な取り組
みがなされ、また多様な行政サービスや介護保険事業があり、
多くの方が利用をしています。しかし、閉じこもり傾向がある
方の利用は難しく、行政、地域ボランティアが利用を促す支援
策を模索していたことが研究の始まりです。
研究では、主体的行動を促す理論として広く活用されるAlbert
Banduraの社会的認知理論や自己効力理論、Prochaskaらによる
トランスセオ・レティカルモデルをフレームワークとして個人
要因へ介入する外出を促すプログラムを作成し、横断研究、質
的研究、混合研究、RCTでプログラムの有効性の確認を、実装
研究で地域での実施可能生の検証を行っています(科学研費助
成金を利用)。地域住民を巻き込んだ活動を行うことで、『住
民にコミュニティの一員という感覚が生まれる⇒地域の人との
信頼をベースとした人間関係が生まれる⇒ここで老後を過ごし
ても安心という感覚が生まれる⇒主観的健康感の向上につなが
る』などの効果を確認しています(Ohashi,2023.6)。そのため
地域住民の「健康寿命の延伸」に向け“住民と協働”で行うこと
を大切に活動しています。
【概 要】行政機関、企業、地域ボランティアと協働による閉じこもり傾
向の母子や高齢期の外出を促す個人要因へ働きかける地域支援
への取り組み
研究のきっかけは、地域にはボランティアが中心となり住民の
外出や顔見知りの機会を設けるカフェサロンなど様々な取り組
みがなされ、また多様な行政サービスや介護保険事業があり、
多くの方が利用をしています。しかし、閉じこもり傾向がある
方の利用は難しく、行政、地域ボランティアが利用を促す支援
策を模索していたことが研究の始まりです。
研究では、主体的行動を促す理論として広く活用されるAlbert
Banduraの社会的認知理論や自己効力理論、Prochaskaらによる
トランスセオ・レティカルモデルをフレームワークとして個人
要因へ介入する外出を促すプログラムを作成し、横断研究、質
的研究、混合研究、RCTでプログラムの有効性の確認を、実装
研究で地域での実施可能生の検証を行っています(科学研費助
成金を利用)。地域住民を巻き込んだ活動を行うことで、『住
民にコミュニティの一員という感覚が生まれる⇒地域の人との
信頼をベースとした人間関係が生まれる⇒ここで老後を過ごし
ても安心という感覚が生まれる⇒主観的健康感の向上につなが
る』などの効果を確認しています(Ohashi,2023.6)。そのため
地域住民の「健康寿命の延伸」に向け“住民と協働”で行うこと
を大切に活動しています。
【登壇者3】志垣智子講師
【概 要】民間助成等の採択により、データ提供・フィールドの共有をお
願いし、継続的な関係構築を行った。卒論のテーマに設定し、
関連したキャリアへ進んだ学生や講義の一環で研究助成で提供
していただいたフィールド先に学生を連れて行き、主体的・実
践的な学びを実施した事例を紹介した。
・平成23年度笹川科学研究助成「神戸市中央市民病院診療録に基
づいた1995年兵庫県南部地震に伴う波及的人的被害発生危険度
評価」(代表)
・令和4年度三重大学地域共創基盤の強化事業「三重紀北消防組
合救急活動記録に基づくコロナ禍における地域の潜在的危険度
評価」(代表)
【概 要】民間助成等の採択により、データ提供・フィールドの共有をお
願いし、継続的な関係構築を行った。卒論のテーマに設定し、
関連したキャリアへ進んだ学生や講義の一環で研究助成で提供
していただいたフィールド先に学生を連れて行き、主体的・実
践的な学びを実施した事例を紹介した。
・平成23年度笹川科学研究助成「神戸市中央市民病院診療録に基
づいた1995年兵庫県南部地震に伴う波及的人的被害発生危険度
評価」(代表)
・令和4年度三重大学地域共創基盤の強化事業「三重紀北消防組
合救急活動記録に基づくコロナ禍における地域の潜在的危険度
評価」(代表)
2018年度スマートエイジングセミナー
2019年2月7日(木)本学70周年記念館で「スマートエイジング」
セミナーを開催しました。
本セミナーでは、人間科学研究科教授である循環器専門医の八尾教授と
死生観哲学者の平等教授がそれぞれのご専門の立場から賢く老いる秘訣
を話しました。
八尾教授は「日本における少子高齢化の進行は社会構造の変化がもたら
した結果であり、その変化に合わせた生き方を考えなければならない状
況にあること」を話しました。
平等教授は「〈老い〉を生きづらい時代」を生きる。人生80年の現代、
私たちが〈老い〉を受容しづらいのはなぜか、人間観から考え直す必要
性を問題提起しました。
人間科学研究科では哲学や健康医学以外にも実社会で役立つ高度な専門
知識を学修するカリキュラムを用意しています。
【大学院人間科学研究科ホームページへ】
セミナーを開催しました。
本セミナーでは、人間科学研究科教授である循環器専門医の八尾教授と
死生観哲学者の平等教授がそれぞれのご専門の立場から賢く老いる秘訣
を話しました。
八尾教授は「日本における少子高齢化の進行は社会構造の変化がもたら
した結果であり、その変化に合わせた生き方を考えなければならない状
況にあること」を話しました。
平等教授は「〈老い〉を生きづらい時代」を生きる。人生80年の現代、
私たちが〈老い〉を受容しづらいのはなぜか、人間観から考え直す必要
性を問題提起しました。
人間科学研究科では哲学や健康医学以外にも実社会で役立つ高度な専門
知識を学修するカリキュラムを用意しています。
【大学院人間科学研究科ホームページへ】