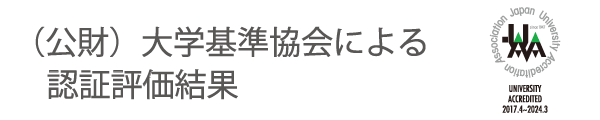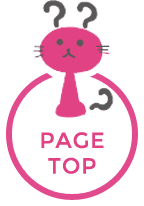2024/11/1
演習を終えて、登録養成課程の感想
はじめまして。大阪経済大学登録養成課程6期生の矢部正和と申します。年齢は50歳、大阪最南部に在住し、妻と2人の娘がいます。平成10年に新卒で入社した中小企業向けのITサービスを提供する企業において、現在も営業マネージャーとして勤務しています。
2月から始まった養成課程ですが、10月末現在で全ての演習科目が終了し、あとは3社の実務実習を残すのみとなりました。入学前から現在に至るまでの登録養成課程に対する私なりの素直な感想を述べたいと思います。大阪経済大学の登録養成課程を検討されている方にとって、何かしら参考になれば幸いです。
まず、私の場合、中小企業診断士の勉強を始めた時点から、登録養成課程への入学は選択肢にありました。理由は、既に中小企業診断士として活躍され、しっかり稼いでいる身近な先輩から、「養成課程の修了生は総じて優秀で、仕事ができる」、「授業料はすぐに回収できる。診断士として活躍したいなら十分に入学する価値がある」と聞いていたためです。
全国には様々な養成課程がありますが、通学に便利な北浜で働きながら学べること、期間が1年で修了すること、講義が私にとって学びたい内容であったこと、以上の理由から、大阪経済大学の登録養成課程を本命にしていました。1次試験合格までは計画通りに進みましたが、2次試験は残念ながら不合格。しかし、本命であった大阪経済大学の登録養成課程に合格・入学できたことは、私の目標の達成に向けて大きな前進でした。
「想像していた以上に日々が充実している」、「登録養成課程を選んで正解だった」、これが私の素直な感想です。
授業のある月曜と水曜は、自宅が遠いため、帰宅時間は23時を過ぎます。そのため、平日の仕事は毎朝6時過ぎから始め、現在の職務に影響が出ないように頑張っています。一見、「大変そう」と思われるかもしれません。確かに楽ではなく、提出期限がタイトで難易度も高い課題の提出と、会社の繁忙期が重なった時や、体調が優れないときなど大変な場面も多々ありましたが、何とかやってきました。私の性格は元来、「真面目や勤勉」とは程遠く、どちらかというと「怠慢なタイプ」でした。そのような私でも、これまで頑張れているポイントを3つ、自分なりに整理してみました。
ポイント1.志望動機が明確である
私が中小企業診断士の資格取得を目指した理由は、現在の仕事に関連しています。平成10年に新卒で営業職として採用されましたが、当時の日々の活動は中小企業、いわゆる町工場への飛込み営業が中心で、ITサービスを提供してはいるものの、ITという響きとは程遠い泥臭い毎日でした。まずは話を聞いてもらうだけで精一杯、契約を取るためには、心身ともに大変な労力が必要な時代でした。長らくこのような活動を続けるうちに、取引が始まり親密になった中小企業の社長から、経営に関する悩みを相談される機会が増えてきました。今でも複数の社長と親しくしており、付き合いは20年を超えています。このような経験から、「孤独な社長の様々な悩みに対して、IT以外の分野でも役に立ちたい」と考え、中小企業診断士の資格取得を漠然と考えるようになりました。
2021年の48歳の夏、プライベートで様々な出来事が重なったことで、人生の後半戦をどのように生きるか、真剣に考える機会がありました。その結果、これまでも漠然と考えていましたが、「50歳から中小企業診断士として活動する」と一念発起し、2022年2月から資格取得の勉強を始めました。
私が中小企業診断士を目指した動機はこのようなものでしたが、養成課程の同期も、それぞれがしっかりした目標や将来のビジョンを持っておられます。時間とお金を費やし、気力と体力を維持しながら学び続けるには、「資格が欲しい」だけでなく、明確な目標や将来のビジョンがあることが重要であると感じています。
ポイント2.関係者の協力と理解が得られている
養成課程中は、在職中の方にとって仕事のスケジュール調整が重要になります。月曜と水曜の夜間は残業ができず、実務実習期間中は、平日の水曜日の休暇取得が必要になります。ほとんどの土日は終日授業があるため、家族と過ごす時間も限られます。私の場合、幸いにも家族と職場の理解が得られたため、毎回時間通りに授業に参加し、講義に集中することができています。
しかし、同期の中には、職場との調整や業務の多忙さから、参加に苦労されている方もいらっしゃいます。授業の密度が濃く、予習復習も必要なため、時間通りに授業に参加し、集中して取り組むためには、家族や職場をはじめとする関係者との事前の合意が非常に重要であると思います。
ポイント3.尊敬できる先生や仲間が多数存在する
入学当初は、本当に不安だらけでした。まわりの同期が優秀すぎて、自分のレベルの低さが露呈するのが怖くて、何をするのにもビクビクしていました。しかし、一か月も経たない内に、不安は解消されました。講義だけでなく、グループディスカッションや、皆の前で発表する機会が何度もあるため、失敗することや、わからないことが悪い事ではないと気づいたからです。
24名の同期は、年齢も性別も、これまでの職歴も、資格取得を目指す動機も全て異なります。多様なメンバーと密に接することで、それぞれの個性や優れた能力、自分に無い能力や考え方に触れることで、多様な視点や考え方を学ぶことができます。逆に、今までは自分では当たり前にできていたことが、実は人よりも長けている能力であることに気付けたりもします。
異なる考え方を否定するのではなく、お互いに様々な考え方や価値観を柔軟に受け入れることで、信頼関係が構築され、同期間での相乗効果が生まれているのではないかと思います。
講師の先生方も、専門知識の提供だけでなく、中小企業の社長との向き合い方や、中小企業診断士としての心構えをしっかりと指導してくださいます。すでに中小企業診断士として、長らく実務に携わってこられた講師の先生方のリアルな体験を聴けることも、養成課程ならではの貴重な機会ではないかと思います。講師の先生方の得意分野やスタンスもまちまちで、同じ内容であっても様々な角度から学べることで、より理解が深まっていくのを感じています。
養成課程の先輩方によるサポーター制度も有難いです。講義内容に関する質問に限らず、実際に中小企業診断士になられてからの具体的なお話が身近に聞けるので、卒業後の活動についても不安が解消され、大変助かっています。
余談ですが、養成課程が始まってから、同期と酒を飲みに行かなかった土日は数えるほどしかありません。それくらい仲が深まっていきます。入学の2月から今日まで大変な日々でしたが、終わりが近づくにつれ、寂しさを感じるようになりました。残りは実務実習だけですが、最後までしっかり取り組みたいと思います。
中小企業診断士を目指す動機が明確で、職場や家族など自身の関係者から協力や理解が得られるのであれば、大阪経済大学の登録養成課程は選択肢として非常に価値があると思います。
拙い文書で失礼しましたが、養成課程で得た学びは、私の人生において、非常に貴重なものでした。同じ志を持つ方々にとっても素晴らしい選択肢になると確信しています。
大阪経済大学の登録養成課程への挑戦を検討されている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
※個別で聞きたいことがあれば、何でもお答えします。お気軽にお声がけください。