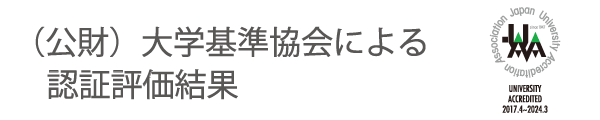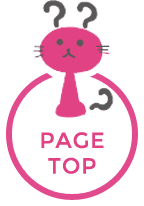閻 立(経済学部教授)
閻立所員
〔専門分野〕 日中近代関係史、中国近代史
〔最終学歴〕 東京大学大学院総合文化研究科後期博士課程
〔取得学位〕 博士(学術)
〔最終学歴〕 東京大学大学院総合文化研究科後期博士課程
〔取得学位〕 博士(学術)
<論文 その他>
「清末の満州開放論について」
(『大阪経大論集』第68巻第6号、193~206頁、2018年3月)
(『大阪経大論集』第68巻第6号、193~206頁、2018年3月)
「20世紀初頭の中国における不平等条約改正への始動と対外交渉」
(『大阪経大論集』第66巻第2号、27~42頁、2015年7月)
「《大清国籍条例》制定過程的考証」(中国語)
(『史林』(上海社会科学院)2013年第1期、97~106頁、2013年2月)
「『大清国籍条例』の制定・施行と日本」
(『大阪経大論集』第63巻第4号、283~297頁、2012年11月)
「日清戦争後の清韓関係―清韓通商条約の締結過程をめぐって」
(『経済史研究』15号、37~55頁、2012年1月)
「一八六〇年代における上海道台の日本観」
(『経済史研究』14号、157~166頁、2011年1月)
「一八六七年における浜松・佐倉藩士の上海視察」
(『大阪経大論集』第61巻第2号、164~146頁、2010年7月)
「近代日清関係の形成―― 一八六〇~七〇年代――」
(『東アジア経済史研究 第一集』大阪経済大学日本経済史研究所編、109~186頁、思文閣出版、2010年2月)
「清朝同治年間における幕末期日本の位置づけ――幕府の上海派遣を中心として」
(『大阪経大論集』第59巻第1号、83~99頁、2008年5月)
「《大清国籍条例》制定過程的考証」(中国語)
(『史林』(上海社会科学院)2013年第1期、97~106頁、2013年2月)
「『大清国籍条例』の制定・施行と日本」
(『大阪経大論集』第63巻第4号、283~297頁、2012年11月)
「日清戦争後の清韓関係―清韓通商条約の締結過程をめぐって」
(『経済史研究』15号、37~55頁、2012年1月)
「一八六〇年代における上海道台の日本観」
(『経済史研究』14号、157~166頁、2011年1月)
「一八六七年における浜松・佐倉藩士の上海視察」
(『大阪経大論集』第61巻第2号、164~146頁、2010年7月)
「近代日清関係の形成―― 一八六〇~七〇年代――」
(『東アジア経済史研究 第一集』大阪経済大学日本経済史研究所編、109~186頁、思文閣出版、2010年2月)
「清朝同治年間における幕末期日本の位置づけ――幕府の上海派遣を中心として」
(『大阪経大論集』第59巻第1号、83~99頁、2008年5月)
〔最近の動向〕
近年、清末新政期における東三省の建省改制(1907年)の過程とその意義について研究を行ってきました。これまでに、日本および中国での学会発表や論文発表を通じて、その研究成果を公表してきました。
今後は、東三省における諮議局の設置について研究を進めていきたいと考えています。1907年、清朝政府は『各省諮議局章程』を公布し、各省に諮議局の設置を命じました。先行研究は主に直隷省、江蘇省、浙江省に集中しており、諮議局を「郷紳権力の拡大」として捉える傾向があります。これに対して、奉天・吉林・黒竜江の三省(東三省)は、行省制が導入されたばかりであるうえ、日露両国の勢力が浸透していたため、諮議局の設置と運営には独自性および代表性が見られます。この研究を進めることにより、辺境地域における立憲制度の特殊性を解明するとともに、「中央―地方―日露」という多元的な視点から諮議局を分析する新たな視座を提示することが可能になります。
(2025年5月)