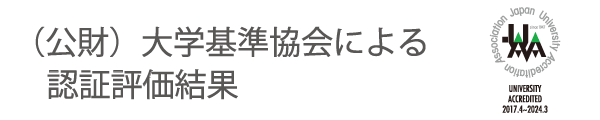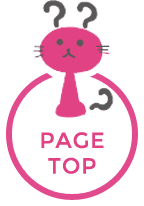藤井 大輔(経済学部講師)
藤井大輔所員
〔専門分野〕 経済政策、応用経済学、中国経済論
〔最終学歴〕 神戸大学
〔取得学位〕 神戸大学博士(経済学)
〔研究課題〕 中国と東南アジアの経済交流
〔研究業績〕 本学のデータベースはこちら
<著書>
梶谷懐・藤井大輔編『現代中国経済論』[第2版]、ミネルヴァ書房、2018年
<論文>
Kai Kajitani and Daisuke Fujii (2016) "Spatial analysis of competition among local governments and the price of land: the case of Zhejiang Province," Journal of Chinese Economic and Business Studies, Vol. 14, Issue 3, pp 229-242.
「地方政府間競争と財政の持続可能性」
(加藤弘之・梶谷懐編著『二重の罠を超えて進む中国型資本主義-「曖昧な制度」の実証分析』第3章、63~83頁、ミネルヴァ書房、2016年)
「GISデータを用いた中国の製造業立地の空間構造分析」
(『比較経済体制研究』第21号,5-22頁,2015年)
「競争する地方政府」
(『中国長江デルタの都市化と産業集積』勁草書房、第2章、2012年)
第1部第3章「産業集積地図の作成方法」、第2部「地図編」
(『中国長江デルタ産業集積地図』早稲田大学現代中国研究所、2012年)
「中国の外資吸収政策の変化と長江デルタにおける外資企業の立地選択の動向」
(『中国経済研究』、第8巻第1号、40-54頁、2011年)
「中国の公共投資と経済発展」(『博士論文』(神戸大学)2009年3月)
「中国の政府間財政政策と財政構造の変遷」(『六甲台論集』第55巻第3号、33-53 頁、2009年)
〔最近の動向〕
中国が2013年から実施している「一帯一路」は、東南アジア各国との経済交流を加速させた。受け入れ側の東南アジアから見ると、経済成長に必須である資金や技術を受けられる一方、債務返済や環境問題、現地社会とのコンフリクト等ネガティブな側面も見られている。さらに細かく見ると、受け入れ側の経済発展水準によって、中国との融資、技術提供の条件も異なっている。例えば、鉄道建設を例にとると、ラオスは中国主導で融資や技術の提供を受けた。その一方、同じく鉄道を建設しているタイは中国との合弁で事業を進めているものの、融資利率が高かったこともありタイは自前資金で建設を進めている。
本年度は、タイやラオスといったインドシナ半島の国々で実施されているインフラ建設案件を中心に事例研究を進める予定である。
(2025年5月)