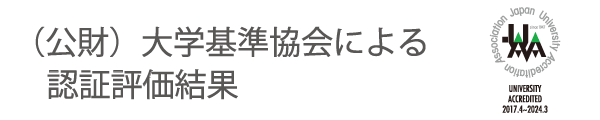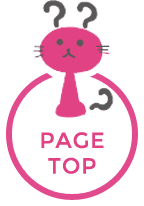強い農業の実現
「強い農業の実現」 キヤノングローバル戦略 研究所 研究主幹 山下 一仁 氏
今回の講師は、キャノングローバル戦略研究所・研究主幹で、経済産業研究所・上席研究員の山下一仁氏(農学博士)で、講義テーマは「強い農業の実現」。農林省〜農水省時代の30年に及ぶ体験や、その後の研究の知見などをもとに、日本の農業の現状やポテンシャル、日本の農業政策・農業経営の問題と今後などについて講義した。
山下氏はまず、アベノミクスが掲げる農業所得倍増戦略の農林水産物の輸出拡大について「日本の農産物、特に米は品質は良いが世界一高く、価格的な競争力がない。日本は米の価格を高くすることで農家の収入を確保する減反政策を取り続け、農業の抜本的体質改善を行ってこなかった」と指摘。米の関税が導入された減反政策が施行された歴史的経緯などを説明したうえで、高い関税で保護しても農業は衰退しているとデータをもとに説明し、「日本の農業の衰退の原因は日本国内にある」と強調。また零細で非効率的な農家が多く存在している実態をデータで解説。関税による保護に異論を唱えた。
そして日本の農業が持つポテンシャルについて「中国沿海部には富裕層が多く魅力的な市場が存在する。農村部の労働コストが上がれば価格に反映され、日本の米の価格競争力が上がる」として、減反を廃止して米の価格を下げることで日本の米が世界市場に打って出られるとアピール。また労働のピークを均すことや標高差による中山間農業、国民性などによる嗜好の違いや国際分業による可能性や成功例なども紹介した。
そして農業発展の方策として、①価格を上げる②生産量を上げる③コストを下げることが必要で、比較的簡単にできる方策はコストを下げることだと説明。集約化により農業の規模を拡大して単収を上げコスト削減する必要性を説いた。そのための方策として食料安全保障は維持できるが消費者は高い価格を負担することになる関税か、食料安全保障などは減少するが安い価格を享受できる自由貿易を掲げたうえで、「最適な政策は、自由貿易で関税を撤廃し安い価格を実現、かつ財政負担で農家を保護する直接支払いで生産を維持しつつ、食料安全保障や多面的機能を維持することだ」と指摘。
提案として、「耕作放棄の原因は米価が下がっていること。主要農家に直接支払いをすることで規模が拡大して生産性が上がり収益も上がる」とアピールした。そして「マーケットが減少する人口減少の時代には、自由貿易こそが食料安全保障の基礎となる。衰退を座して待つよりは米国のような直接支払いによる構造改革に賭けるべき。それ以外に日本農業の維持発展はない」と結論づけた。