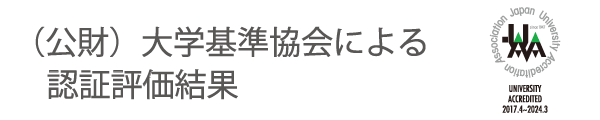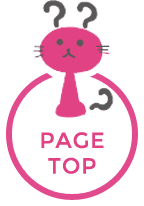【2022年度】 中村健二ゼミ「土木インフラデータチャレンジ2022・アイデアソン」に参加
情報科学で交通・インフラの課題解決を図るアイデアを学生が創出
2022年10月15日(土)、中村ゼミが一般社団法人土木学会(※)主催の「土木学会インフラデータチャレンジ2022〜ウェビナー&アイデアソン」に参加しました。土木学会インフラデータチャレンジとは、インフラデータや交通関連のビッグデータを参加者に提供し、行政などのインフラ管理者や交通機関の利用者が抱える課題を解決するアイデアを考えるコンテストです。
※土木工学の進歩や土木事業の発達、さらには土木技術者の資質向上を図り、学術文化の進展と社会の発展に役立つことを目的とする団体。
プレゼンテーションの厳しい条件もゼミでの鍛錬のおかげで難なくクリア
今回の土木学会インフラデータチャレンジ2022(以下IDC2022)は、オンラインで開催され、中村ゼミのゼミ生5人以外に、山口大学、法政大学、大阪電気通信大学、摂南大学の学生たちが参加しました。
このIDC2022は通常のアイデア創出、プレゼンテーションイベントとは異なるスタイルで開催されます。それが名称にも掲げられている「アイデアソン」です。アイデアソンはアイデアとマラソンを掛け合わせた造語で、特定のテーマのもとメンバーを集め、グループディスカッションなどを通じて新たなアイデアの創出やビジネスモデルの構築を短期間で取り組みます。
IDC2022では、参加した学生を5〜6名ずつ8つにグルーピング。即席でつくられたグループのメンバーたちと、1時間という短い時間で課題解決のアイデアを議論してカタチにし、プレゼンテーション用のスライドまで作成しなければなりません。アイデアを思いつくだけでも時間がかかり苦戦しそうですが、中村ゼミの学生たちは「まったく苦と感じなかった」といいます。というのも、中村ゼミは大阪経済大学屈指の厳しさで知られるゼミ。中村先生によると、「社会で活躍できるように訓練、いや修行といっていいほど、学生を鍛え上げていく」とのことで、常日頃からアイデアソンのようなアイデア創出やプレゼンテーションに対応できる力を磨いているそうです。
例えば、中村ゼミではグループワークを通じて100案ものビジネスプラン、アイデアを創出し、プレゼンテーションする課題に取り組みます。100案をカタチにすることも大変ですが、プレゼンテーションでは中村先生から徹底的に質問をなげかけられるため、応答に窮してしまう学生も。「どんな質問や指摘にも対応できるよう、深い部分まで考え抜いて準備しなければ、プランの実現はおろか実社会では通用しません。学生の間に数多く失敗し、時には恥ずかしい思いをすることも必要です」と中村先生。その言葉には厳しさの中に、このゼミで学生に成長して欲しいという思いがあふれています。今回のIDC2022でも、学生たちは各グループで、中村ゼミで築いた力を遺憾なく発揮。積極的にアイデアを提案して議論するとともに、考えを迅速にまとめてスライドを作成したり、プレゼンテーションのスピーカーを務めたりしました。
そんなゼミ生を含む8グループの発表内容は、住民や観光客の移動データを収集し、それをもとにスムーズな移動手段や移動経路を案内するアプリであったり、オンライン上に再現した都市をユーザーがバーチャル歩行することで道路の不備や危険地帯を見つけてフィードバックする取り組みであったり、最新のテクノロジーを活かした斬新なものばかりでした。
土木学会インフラデータチャレンジは、アイデアの創出が目的なので、順位の決定や表彰はありません。発表後は、それぞれの内容について、主催者から「短時間で良いアイデアが創出された」「地域のインフラの課題解決につながる可能性を感じた」といった評価を受けました。
ゼミで培った力をさらにバーションアップさせることに期待
今回のIDC2022で奮闘した5人のゼミ生に向けて、中村先生は「土木やインフラの課題というと遠い存在のように感じますが、交通網をはじめとするインフラは誰もが生きていくうえで欠かせないものであり、大変身近な存在です。昨今は、例えば道路が傷んでいる、公園の遊具が壊れているといったことをアプリで行政にレポートするといった“市民協働”による課題解決も進んでいます。今回、ゼミ生はこういった地域社会の動きを察知しつつ、インフラ・交通の課題を自分事として捉えて、良いアイデアを創出してくれたと思います」と評価。今後もゼミで修行を重ね、UDC(※)というコンテストへのチャレンジや、就職、将来に活かしてほしいと大きな期待を寄せていました。
※UDC:アーバンデータチャレンジ。地方自治体などが保有するデータを用いた地域課題解決を目指すコンテスト。
参加者の声
広田 椋祐さん(情報社会学部3年)
日本の交通環境は自動車と歩行者に区分されていることが大半で、自転車が走行しにくく、私もグループのメンバーも自転車に乗っている際、危ないと感じることがありました。かといって、既存の呼びかけや罰則だけでは安全意識は高まらないことから、安全な自動車運転を行ったドライバーに対してポイントを付与、活用できるアプリの開発を提案しました。メンバーは私以外、同じ大学で土木を専攻している学生たちで、初めは緊張しましたが、中村ゼミで鍛えられているコミュニケーション力が役立ちました。また、私が専攻する情報科学分野と異なる分野を学ぶ学生たちと議論できたことは刺激となり、視点がさらに広がったと思います。
芝 純一さん(情報社会学部3年)
私たちが取り上げたのは、長野県伊那市で進められているオンライン医療診療車両を活用した医療サービスです。このサービスは、看護師が医療診療車両に乗って、通院困難な高齢者の自宅を訪問し、病院にいる医師とオンラインでつないで診療を行います。現状は利用者や地域ごとの需要を把握しきれていないため、効率よく訪問できていないといった課題があります。そこで近年、導入事例が増えてきた事前予約制のオンデマンドバスの仕組みと、AIによる需要状況の予測を組み合わせることで、医療診療車両を効率的に活用するアイデアを考えました。今後もこういったイベントに積極的に参加し、私が目標にしている農業分野での課題解決に貢献できる力を身に付けたいです。