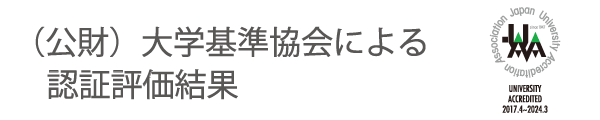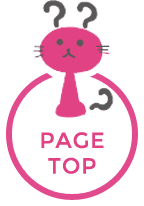【2023年度】大橋純子ゼミ 地域の小・中学校で、「認知症に関する講話」を実施
小・中学生にも分かりやすい説明資料を作成
人間科学部大橋純子教授が担当する1年次の「基礎演習」の授業では、小・中学校での「認知症に関する講話」の実施に取り組みました。大橋教授は、認知症の高齢者をはじめ、さまざまな人が共に暮らせる社会づくりを研究テーマとしています。「社会が変われば、認知症や障がいのある方も不自由なく暮らせます。そうした社会づくりの担い手になってもらえるよう、小・中学生のうちから認知症への理解を深めるというのが今回の取り組みの狙いです」と、大橋教授は説明します。大橋教授が学生たちに講話の実施について提案したところ、やってみたいとの声があがり、取り組みがスタートしました。
今回、協力いただいたのは、本学近隣に所在する大隅西小学校、瑞光中学校です。学生たちは、小学校、中学校、それぞれ7名のチームに分かれ、事前準備から当日の進行まで主体的にプロジェクトを進めていきました。まずは学生自身が認知症に関する知識を調べて学んだ後、パワーポイントでスライドを作成します。学生たちが特にこだわったのは、小学生や中学生に分かりやすい講話を行うこと。小学生チームは、子どもたちの緊張をほぐすために、認知症に関するクイズから講話を始めるアイデアを取り入れました。また、中学生チームは、認知症の症状を説明するパートで、文字で説明するよりも理解しやすくなるとの考えから、学生自身が認知症の人を演じる動画を制作しました。
小・中学生と大学生では語彙力に差があるため、言葉選びにも配慮したと言います。「大橋先生からの助言があり、伝えようとする相手に合わせた表現の仕方をしなければならないと気付きました。メンバーとも話し合い、言葉選び、スライドの見やすさなどを十分に検討して準備を進めました」と、学生は取り組みの様子を振り返ります。
コーチングで認知症の人に対する理解を促す
今回の講話は、小学生チームは約80名の小学5・6年生に、中学生チームは約170名の中学2年生を対象に実施しました。どちらの講話も、認知症についての知識を伝えるだけでなく、質問などの問いかけによって、小・中学生が自ら考え答えを引き出す構成となっています。
小学校は体育館で参加児童と学生たちが一堂に会して実施。中学校は配信元の教室から5クラスに配信するオンライン形式で行い、各クラスに1名ずつ学生が付いて進行をサポートしました。「見当識障害」や「幻視」など症状別に、認知症の人に見えている世界を小学生には漫画を、中学生には作成した動画を見てもらった上で、「どのような感情がわいてきましたか」「自分ならどうして欲しかったですか」と、問いかけます。学生たちは小・中学生のグループでの話し合いを見守りつつ、質問にも対応していました。中学校を担当した学生の一人は「説明をよく理解できていない生徒に補足説明を行ったり、話し合いがうまくできていないグループには考えるヒントとなる声掛けをしました」と話します。グループワーク後の意見発表では、小・中学生から「何も分からないから怖くなる」「自分の気持ちを分かってくれなくて悲しくなる」「やさしくしてほしい」「気持ちに寄り添ってほしい」といった意見が出ました。
講話終了後のアンケートでも、「認知症の人は怖いと思っていたけれど、これからはしっかりと話を聞いてあげようと思った」「どんな症状があるのかを知り、接し方も分かった」と、理解が深まったことが分かるコメントが寄せられました。学生たちは「私たちの狙い通りの答えが引き出せた」と、手応えを感じられた様子。また、「認知症に幻視という症状があるのを知らなかったといった声も聞かれ、知識を深める役に立てて良かった」と、取り組みの成果が実感できたことを喜びました。
取り組みを終えた学生は、「伝える相手のことを考える視点が身に付いた」「教員免許の取得を目指しているので、学校の先生の生徒への接し方を見て勉強になった」「学外の人の前で発表できたのは、いい経験になった」「自分の知識不足を感じた場面があったので、この反省点を今後に活かしたい」と、それぞれ学びを得られたと話します。自ら考えて行動できた今回の経験は、これからの大学での学びに間違いなく活きてくるでしょう。
大橋教授は、「何を伝えたいのか、相手に伝わる仕立てができているか、という視点を重視し、学生自身でしっかりと考えて活動できていました。講話当日も、ただ台本通りに進めるのではなく、小・中学生の反応を見て臨機応変に対応できていたところが良かったです。主体的に課題に向き合う場を用意し、客観的な視点からの助言を学生たちに伝えて自ら考えることを促す中で、彼らが持つ力が引き出せたと感じています」と、学生たちの取り組み姿勢を評価しました。「今回、自分たちの働きかけによって、小・中学生の意識を変えられたと学生たちは実感できたでしょう。引き続き、外部の方々とも連携した実践的な学びによって、自分たちの頑張りで社会を変えられるのだと実感してもらえる機会を作っていきたいです」と話す大橋教授。今後も大橋ゼミでは、企業、自治体、教育機関などと連携した取り組みを進めていく計画です。