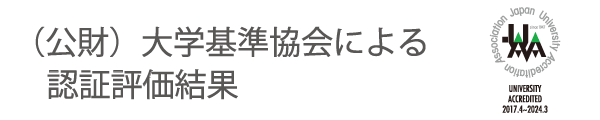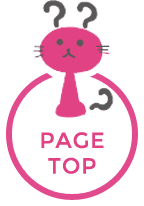2024/5/16
気になる養成課程のあれこれ
大経大診断士登録養成課程6期生の小寺隆聖と申します。
IT企業でSEをしておりましたが、一念発起、中小企業診断士を志し、学習に集中するため退職。その後、なんとか大経大診断士登録養成課程でお世話になることとなり、現在に至ります。
早くも、養成課程が開講してから約3か月が経過しましたが、多様なバックグラウンドと豊富な経験を持つ6期生同期の方々に囲まれながら、日々刺激的な生活を送っております。
今回、養成課程3か月が経過してみて、若輩者の私視点(5/11執筆時点29歳)で気づいたこと刺激的であったことを、養成課程の選考から今までの振り返りとして共有できればと思います。この記事が、これから大阪経済大学中小企業診断士登録養成課程の受講にご興味をお持ちの方の一助となれば幸いです。
まずは、読者の方が一番気にされているであろう目下の選考についての経験談
養成課程6期生の選考では、①適性検査・書類審査→②グループディスカッション→③最終面接・小論文の3段階の選考フローに乗りました。書類審査にはあふれんばかりの熱意を書き記し、なんとかグループディスカッション(GD)に進みます。GDの待合室には、経験豊富そうな方々(受験生であり、実際経験豊富であられる)がずらりと座しておられるのを見て萎縮に萎縮を重ね、緊張で声も出ませんでしたが、グループの方の優しさに恵まれ、気合いで積極的に討論発表を終え、最終面接・小論文へと進みました。
ちなみに、GDのテーマは「中小企業の今後3-5年以内の課題について」であり、中小企業白書からテーマを選定し発表という流れでした。最終面接は質疑応答が30分程度で、小論文は事業承継がテーマでした。
さて、ここからは本題の、養成課程に入ってからの3か月について
まず、3か月で何をどのように学んだのか。
【何を】コンサルタントとして必要な基本的な読んで聞いて書く能力、リサーチ力・ロジカルシンキング・プレゼンテーション・ライティング・資料作成・傾聴・人事組織診断・マーケティング診断・財務会計診断・事業承継・コンサルプロセス・経営計画作成・ファシリテーション などの能力
【どのように】インプット(座学)→グループワーク→発表 を繰り返し、授業後はレポートを書いて提出 のサイクルをひたすら繰り返し実施します。
(課題図書や参考文献なども教えていただき、大変ためになります。)
膨大な量の知識を毎週四回の講義で一気に詰め込みますので、予復習は欠かせませんし、ついていくのに精一杯ですが、内容はどれも実務的であり、業務に即した実践的な知識がたくさん得られます。
ちなみに、ここまでの出席時間を計算すると計160時間程でした。(5/11時点)
別途レポート作成・予習復習に費やした時間は、ざっくり20~40時間程度です
6月からは診断実習が始まりますので、気を引き締めて、学んだ内容を存分に発揮してまいりたいと思います。
6期生プロフィール
男性17名、 女性7名 「当課程史上最も女性比率が高い」
参考)R4の診断士筆記試験は女性合格比率が10%弱
独立志望の方が約半数
年齢層は29歳~50代まで
四国から大阪へ一時的に居を構えて通われている方もおられます。
同期の皆様の職種は、
M&Aエージェント、金融機関、経営者、弁護士、SE、大企業開発職・営業マンの方など多彩な業種で、熱意のある優秀な方ばかりで、専門家の方々の知見は大変参考になります。
いかがでしたでしょうか?
私が紹介させていただいたのは、大経大診断士登録養成課程のほんの始まりの3か月の部分だけですが、本養成課程の受講を検討されている方は、今後の更新で経営診断実習について書かれた記事についても、ご参考にされるのが良いかと思います。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。
6期生 小寺隆聖